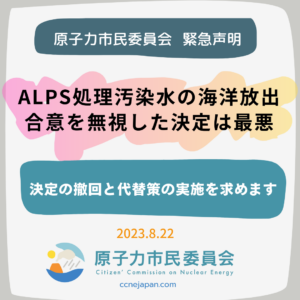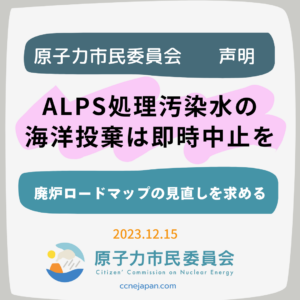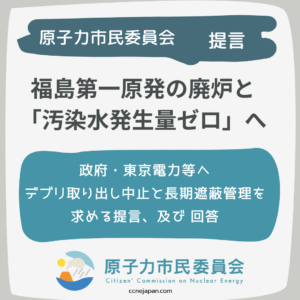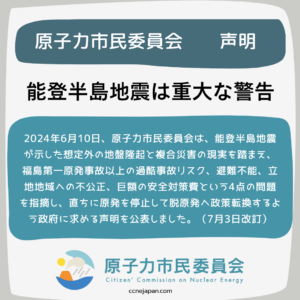原子力市民委員会は2024年6月10日、能登半島地震を従来想定を超える自然災害からの重大な警告として受け止め、日本の原子力規制や防災計画の前提が崩れたことを指摘し、直ちに稼働中原発を停止し、脱原発への政策転換を求める声明を公表しました。(7月3日一部改訂)
声明
声明: 能登半島地震を自然からの重大な警告と受け止め、改めて脱原発への政策転換を呼びかける
2024年6月10日(7月3日改訂版)
原子力市民委員会
座 長 大島堅一
委 員 後藤 忍 後藤政志 清水奈名子
茅野恒秀 松久保肇 武藤類子
吉田明子
2024年1月1日の能登半島地震は、沿岸部の断層が150 kmにわたって連動して起こった。これによって能登半島北岸から西岸にかけて90kmにわたる海岸線付近の土地が最大4mも隆起するなど、地震の規模は、従来の予想を大きく上回った。
この地震で示された事実からすれば、規制基準や原子力災害対策指針の見直しや、既存の原発の基準地震動の検証や耐震補強等だけで、原発の安全性が確保できるとは考えられない。地震・津波といった自然災害が頻繁に発生する日本において、原発を稼働させることには容認しがたい大きなリスクをともなう。直ちに稼働している原発を停止し、脱原発に向かうべきである。
福島第一原発事故後13年を経て、停止中の北陸電力志賀原発に重大なトラブルが生じなかったとして、原発事故のリスクを軽視する動きが目立つようになっている。原子力規制委員会は、能登半島地震で浮き彫りになった問題から目を背け、基準や指針の見直しや検証をおこなわず、事故発生時の「屋内退避」のあり方や運用に問題を矮小化している。一方、東京電力は、今回の地震で柏崎刈羽原発で最大震度5強が観測されたにもかかわらず、再稼働に対する自治体の同意がないまま核燃料の装荷を強行した。政府は、第7次エネルギー基本計画改定にあたり、福島第一原発事故や能登半島地震から何も学ばず、「原発の活用」を盛り込もうとしている。
能登半島地震から得られる教訓は、原発を稼働すれば、福島第一原発事故と同等か、もしくはそれ以上の深刻な事故が起こりかねないということにある。以下、改めて原発利用にともなう根本的問題を4点指摘し、脱原発にむけた政策転換を求める。
1.福島第一原発事故以上の過酷事故と放射能汚染は起こりうる
能登半島地震によって原発事故が起きなかったのは、志賀原発が運転停止していたため、また、関西電力、中部電力、北陸電力によって計画されていた珠洲原発が、地元住民の反対で建設されなかったためにすぎない。
福島第一原発事故後、大手電力会社や原子力規制委員会は、炉心溶融(メルトダウン)をともなう「過酷事故」が起こりうることを認めるようになった。しかし、格納容器の破損が起き、福島第一原発事故以上の放射能が放出される事故の可能性は完全に無視している。
現行の新規制規準に適合したとしても、炉心溶融から格納容器の大規模な損壊に至る事故は起こりうる1。それは、福島第一原発事故をはるかに上回るような大量の放射能放出をともない、その結果、急性放射線障害を含む深刻な人的被害をもたらす。
起こりうる最悪の原発事故の可能性や規模については、福島第一原発事故以前から議論が重ねられてきた2。今回の能登半島地震で、志賀原発や珠洲原発が稼働していたならば、地震や津波、地盤隆起により、原子炉の緊急停止、または炉心の冷却失敗等により、炉心溶融から大規模な格納容器損壊事故に陥った可能性がある。
放射能汚染は、放出放射能量だけでなく、地形や気象条件によっても左右される。福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、不幸中の幸いとして、西から向きの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ陸の放射能汚染が軽減された3。事故のリスクを把握する際、このような偶然を期待してはならない。志賀原発、あるいは若狭湾沿岸の原発や柏崎刈羽原発をはじめとした原発で過酷事故が起こり、大量の放射能が放出されれば、福島第一原発事故を遙かに超える放射能汚染が拡がる可能性がある。
2.複合災害時に住民は放射線被ばくを避けられない
能登半島地震による地震や津波によって多くの建物が全壊、半壊、一部損壊を被った。道路の多くは土砂崩れ、地割れや隆起、液状化で車両の通行が不可能になった。このような状況の下では、原発事故直後の被ばくを避けるために必要な屋内退避も、避難も全く不可能である。福島第一原発事故においても、放射能の拡散による避難指示のために、救えたはずの津波被災者の救助ができなかった事例や、病院からの避難者が長時間にわたる避難の過程で命を落とす痛ましい事例があった。今回の能登半島地震が、原発事故との複合災害に至っていれば、自宅が倒壊した被災者は、屋内退避で被ばくを防止できず、長期間、救助を待ちながら、被ばくし続けた可能性がある。その上、放射能汚染の広がりが寸断した道路や通信設備などの復旧の妨げとなり、被災者の安否確認や救助活動が、より一層困難になったであろう。
また、後述(補足説明1.の(2))のように、事故炉への緊急対応に必要な機材や人員の搬入・参集にも困難をきたすため、放射能放出への対処が遅れ、被ばく状況が悪化する恐れもある。
3.原発立地地域に重大なリスクをおしつける社会的不公正
能登半島地震は、原発の本質的危険性と避難の困難さを改めて示した。特に、原発立地地域は、多くの場合、人口減少・高齢化、厳しい自然条件などにより、交通・通信、医療・福祉などの社会的インフラが脆弱であり、都市部への電力供給のために大きなリスクにさらされているとも言える。このような社会的不公正を、これ以上、黙認し放置するべきではない。
4.巨額の原発の安全対策費・維持費は誰のためなのか
2011年の東日本大震災以降、新規制基準に適合して再稼働した原発は12基で、新規制基準に適合したが未稼働の原発が5基、審査中が10基、未申請の原発も9基ある。これらに対して、投じられてきた安全対策費は、少なくとも5.8兆円を越える4。さらに、2011〜2020年度の期間に原発の維持に投じられた費用は約17兆円に上る。そのうち保有する原発が1基も運転しなかった年度の維持費の累計額は11.65兆円だった5。これらの費用支出で直接の恩恵を受けたのは原子力産業である。これは同時に電気料金の引き上げによる国民負担増大をもたらした。原発利用を前提とすれば、安全対策工事や維持のための費用支出が不可欠である。一方、脱原発であればこのような費用支出は殆ど不要である。脱原発は、原発の危険性を根本から減らすだけでなく、電気料金の引き下げをもたらし、国民負担を大幅に節約する。過酷事故の回避と費用負担を減らすためにも早期の脱原発が必要である。
以上
補足説明
1.能登半島地震を受けて明らかになった問題点
(1)原発の安全性確保に関して
<規制当局および北陸電力の不適切な対応>
- 能登半島地震に対する原子力規制委員会の姿勢は、「結果として」志賀原発の安全性に問題がなかった、新たな知見があれば今後の規制に取り入れる、というものであり、危機感が根本的に欠如している。
- 北陸電力は、地震直後からの国会議員等からの視察の要請を断り続けた。報道機関の取材を認めたのも、地震発生から2ヶ月以上が経過した3月7日であった。このとき、変圧器などのトラブルのあった箇所はすでに片付けられており、撮影箇所が厳しく制限されるなど、北陸電力は情報開示に消極的であった。原発内部で発生したトラブルに関して第三者が検証できるようにする必要がある。
- 新規制基準に基づき、原発事業者が計画している過酷事故対策では、事業者が事故の状況をリアルタイムで的確に把握し、対処できることが前提とされているが、その前提に無理がある。今回の能登半島地震における北陸電力からの情報発信は、正確性においても迅速性においても、周辺住民をはじめとする社会全体に対して不安を抱かせるものだった。大規模な自然災害に対して、迅速かつ的確に状況把握を行い、関係機関に連絡するということ自体、実現が困難だということを認めるべきである。
<自然災害の想定規模は適切だったのか>
- 原発の潜在的な危険性を考慮し、十分に大きな災害規模を想定してこなかったことに根本的問題がある。『原発ゼロ社会への道』2022年版で指摘したように、「将来起こりうる最大規模」の自然災害を予測し、原発の安全性を確保するなどということは本質的に困難である6。
- これまで原発の設計において、実際に行われてきた地震・津波等の自然災害の想定は、当該原発サイトに影響を及ぼす災害規模を正確に予測しているかのように装いつつも、実質的には、原発の運転を正当化する範囲に留まっていた。福島第一原発事故後の裁判などを通じて明らかになったように、福島第一原発事故をもたらした津波も、「想定外」だったのではなく、政府の地震調査研究推進本部の長期予測に基づく大津波を想定することを、東京電力が拒み、先送りにしていたに過ぎない。
<安全機能喪失の具体的なリスク>
- 地盤隆起は、海からの冷却水の取水を困難にし、炉心冷却機能の喪失につながるリスクを生じさせる。数mにおよぶような地盤の変動は、原発の建屋、設備の損壊、配管破断等をもたらすことになる。なおかつ、そのような規模の地盤の変動を想定した安全設計は不可能である。
- 外部電源が全滅するリスクは解消できない。実際、原子力規制委員会は、外部電源が全滅する可能性があることを認めているため、原子力事業者に対して非常用電源の設置を求めている。しかし、非常用電源にも機能喪失のリスクがある。したがって、全電源喪失のリスクをゼロにすることはできない。
(2)複合災害では、住民避難・原発事故対応・災害復旧が機能不全に陥る
- 自然災害と原発事故の複合災害において、避難、救援は困難である。原子力災害時の防災計画では、PAZ(予防的防護措置を準備する区域:原発5km圏内)の住民を優先的に避難させるために、UPZ(緊急防護措置を準備する区域:5〜30km圏)の住民に屋内退避を求めることになっているが、実際にそのような行動がとられると想定するのは無理がある。原発事故時に、多数の自発的な避難者によって深刻な交通渋滞や事故が発生し、交通インフラが機能不全に陥る可能性が高い。屋内退避による被ばく防護は、大地震・津波などの状況ではまったく機能しないことは明らかである。
- 原発周辺の交通インフラが機能不全に陥れば、事故に対処するために必要となる作業員や専門家等が原発構内に駆けつけることが困難になる。また、構内道路に陥没、地割れや障害物があれば、重大事故等対処設備である可搬式の電源車やポンプ車などの搬入が所定通りにはできなくなる。
- 自然災害で人々が孤立した状況で、さらに放射能汚染が重なった場合の対処が極めて困難なことは明らかである。孤立した集落への支援や救援、アクセスルートや通信手段の復旧作業等が、放射能汚染によって阻まれた場合、孤立した集落の人々は、救助や生活支援物資の支給も受けられない中で、長期間にわたる被ばくを余儀なくされることになる。
(3)「怖くない」程度のリスクだけを語る無責任
- 原子力規制委員会元委員長の田中俊一氏は、新潟県柏崎市での講演で、「複合災害のときは、原子力災害のことを忘れていただきたい。まず原子力災害を忘れて他の自然災害、他の災害から自分の身を守り、命を守ることに専念していただきたい」「原子力災害は、皆様が思い込んでいるほど、そんなに怖いものではない」と述べた7。これは極めて無責任な発言である。自然災害のもとで原子力防災が機能しないという根本問題から人の目をそらし、被ばくリスクについて誤った理解をもたらすものである。
- 福島第一原発事故以前から警告されていた原発事故の被害想定をあらためて見直す必要がある。
- たとえば、1992年に高木仁三郎氏は、柏崎刈羽原発1号機における大事故(冷却材喪失、炉心溶融、水蒸気爆発、格納容器破損による大量の放射能放出という設定)における被害想定として、「柏崎市、刈羽村を中心に早期の死者7000-9000名、急性放射線障害者約6万名(新潟県内)が予測されるとともに、放射能の影響は遠く首都圏にも及び、総被曝線量は約420万人シーベルト(約4.2億人レム)にも達し、がん死者は将来において42万人にものぼると推定される。」と警告した8。
- 前記の田中俊一氏は、「怖いものではない」程度の原発事故しか語っていないが、これからの原発事故に備えるにあたり、田中俊一氏が語った程度の原発事故を想定するだけで許されるのか、高木仁三郎が警告した規模の原発事故が起こりうると考えるのか、冷静に考え直すべきである。
2.福島第一原発事故後の原発の安全規制の欠陥
(1)原発の基本設計を見直さず、追加的な対処でお茶を濁したこと
- 福島第一原発事故に策定された新規制基準では、設計上の想定を超えた事故に備えた過酷事故対策が義務づけられたが、基本的な原子力発電設備の構造や仕組みは、ほとんど福島第一原発事故以前と変わっていない(設備として新たに設置されたのは、一部の原発で、格納容器ベントにフィルタを設置して放射能の放出を抑制する仕組みを追加したことなどに限られる)。
- 設計の想定を超える重大事故(過酷事故)や、それをさらに上回る事故に対する対策は、可搬式の電源車による電源の供給や、ポンプ車による冷却水の補給、さらには、放射性物質の拡散を放水砲で抑制することなど、原発の過酷事故時の対策としては、信頼性の低いものばかりである。
- しかし、能登半島地震で明らかになったことは、原発周辺の道路が寸断され、敷地内の地盤すら大きく変位することがあり得るということである。そのような過酷事故においては、人手による可搬式の設備や対策などが、全く成り立たないこともあり得る。
- 新規制基準は、既存の原発に追加的な対策をすることで、再稼働が可能になる程度に定められたものである。原発の基本設計を見直していない弥縫策であり、過酷事故対策そのものが破綻していると見るべきである。
(2)原子力規制委員会が立地審査指針を棚上げ(放棄)してしまったこと
- 福島第一原発事故を経験した後に、原子力規制から立地審査指針の適用を外したことは、「新規制基準が公衆の安全を守ることを最優先にしているものではない証し」として、原子力市民委員会では新規制規準が策定された当初から批判をしてきた9。原発の運転を正当化することの根本的な無理がここから生じている。この点について下記のような具体的な指摘がある。
石橋克彦氏の指摘(週(週刊金曜日 2024 年 1 月 26 日号)
“(立地審査指針は)原発の立地条件の一つとして、大事故の誘因となるような事象が過去になくて、将来もあるとは考えられないこと、災害を拡大するような事象も少ないことを規定している。”
滝谷紘一氏の指摘(柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者/技術者の会 Newsletter No.15 2021年7月15日)
“「東電が想定し、規制委員会が承認した重大事故の一つ『大破断LOCA+非常用炉心冷却系の機能喪失+全交流動力電源の機能喪失』においては、格納容器内の圧力が所定値を超えないように格納容器圧力逃し装置(フィルタ付きベント装置)を運転員操作で作動させる。この場合、希ガスはフィルタを素通りして捕捉が不可能なので炉内蓄積量の100%が排気筒から放出される評価になる。被ばく線量は放出線源量に単純比例するので、敷地境界での全身被ばく線量は、前掲の基本データを用いると以下の値になる。
- 敷地境界での全身被ばく線量:約2.4 Sv
この値は立地審査指針に定められた判断めやす値0.25 Svのほぼ10倍である。従って、柏崎刈羽6、7号機は、立地審査指針に不適合であり、設置許可取り消しに相当する。」
(3)防災・避難計画の実効性が原発稼働の条件として法制化されていないこと
- 原子力市民委員会は、特別レポート5「原発の安全基準はどうあるべきか」(2017)において、次のように提言した(pp.103~104)。「原子力規制行政として防災・避難計画を検証することを、原発の建設・運転等の許認可に際しての法律上の要件とする必要がある。規制委は新たに〈原子力防災基準〉(仮称)を定め、それに基づく〈原子力防災審査〉(仮称)に合格することを、原子力施設運転の原子炉等規制法上の要件とすべきである。その審査は前記の〈原子力防災庁〉が担うものとする。それが〈原子力防災庁〉の平時(緊急時以外)の主な任務となる。(〈原子力防災庁〉は緊急時にのみ活動すればよい組織ではない。)」
- 現在、政府の「原子力防災会議」が自治体の「地域防災計画(原子力災害対策編)」を承認するかたちとなっている。しかしこれは形式的な承認に過ぎず、実効性を検証する仕組みがない。
- 原発立地自治体からは、原発は国策であり、国が責任を持って原発の必要性を説明すべきであり、防災・避難対策についても国が支援すべきとの声がある。しかし、自治体の「国まかせ」は、住民を危険にさらすものであり、無責任である。深刻な原発事故には、国も責任をとることはできないことは、福島第一原発事故を振り返れば明らかである。
- 深層防護は複合災害では機能しない。原子力施設に求められる深層防護とは、
- 第1層:異常運転や故障の防止
- 第2層:異常運転の制御および故障の検知
- 第3層:発生した事故を設計上の想定内に制御
- 第4層:事故の進展防止・影響緩和・過酷な状態のプラントの制御
- 第5層:大規模な放射能放出による放射線影響の緩和
という5つの層のすべてにおいて、他の層での対策の成否に依存することなく、独立して対策がとられている、ということである。しかし、各層の対策は安全機能が維持できていることを前提にしており、自然災害などによって、利用できるリソースが制限されれば、各層の対応が成立しなくなる。第5層の放射線影響の緩和など、確実にできる保証はない。自然災害等の複合災害では、深層防護がまったく機能しないおそれがある。
(4)武力攻撃のリスク
・武力攻撃は明確な目的を持って企てられる。ロシアのウクライナ侵攻では、武力衝突により原発の安全性が脅かされる事態が現実に生じている9。原子炉本体は言うにおばず、核燃料貯蔵プールが攻撃を受けた場合でも大規模な放射能放出に至る恐れがある。外部電源系統あるいは海水冷却設備等への攻撃で、原発の過酷事故に至るリスクがある。
以上
※改訂版について
文意と根拠を明示する目的で、7月3日付で本文「1.福島第一原発事故以上の過酷事故と放射能汚染は起こりうる」の一部を下記のとおり加筆修正しました。
♦変更前:福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、西向きの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ放射能汚染が軽減された。
♦変更後:福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、不幸中の幸いとして、西からの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ陸の放射能汚染が軽減された(脚注3)。
脚注3:福島第一原発から環境中に放出された放射性物質の量と移動様態については様々なモデルやシミュレーションによる推計があり、定量的な評価にはかなりの幅があるが、日本学術会議(総合工学委員会 原子力事故対応委員分科会)の2014年9月2日付の報告「環境中に放出された放射性物質の輸送沈着過程に関するモデル計算結果の比較」(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf)によれば、大気への総放出量のうち陸域に沈着した比率は27 ± 10%に留まったとされている。青山道夫・山澤弘実・永井晴康(2018)「福島第一原発事故の大気・海洋環境科学的研究の現状」『日本原子力学会誌』60(1):46-50(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja)によれば、事故時に炉内に存在したセシウム137のうち15-20PBqが大気に放出され、その約80%が西部北太平洋に降下したと推計される。これとは別に、3.5±0.7PBq(大気への放出量の42-86%に相当する量)のセシウム137が海に直接漏出したと推計されている(ib. p.47)。
脚注
- 原子力市民委員会 特別レポート5『原発の安全基準はどうあるべきか』(2017)、原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道 ―「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』(2022)の第4章(特に4.3「原発安全性の技術的な争点と新規制基準の欠陥」)を参照されたい。 ↩︎
- 原発事故による被害の検討としては、米原子力委員会による「原子炉安全研究 WASH-1400 」(1975)(主導したマサチューセッツ工科大学教授の名から、「ラスムッセン報告書」と呼ばれる)が参照されることが多い。この報告では、沸騰水型原子炉、加圧水型原子炉について、複数の事故シークエンスを検討し、事故による放射能放出がもたらす人的被害(急性死亡、急性障害、晩発性がん死者など)や、放射能汚染により立入禁止となる面積などを見積もり、経済的な被害規模などを示している。なお、この報告が「最悪の事故」を示したものかという点についても議論があり、それ以上の事故が起こりえないと言うことではない(脚註8参照)。また、Lee et al. (2023), “Radiation Leakage Impact on China, Japan, and South Korea in the Case of Nuclear Power Plant Accidents an Spent Fuel Pool Fires in Northeast Asia: Analysis Using HYSPLIT Simulation Model, Nuclear Power Safety and Governance in East Asia, Taylor & Francis, pp.42-62によれば、大飯原発4号機(福井県)で、炉心溶融後の早期に格納容器破損事故が発生した場合、2021年9月の気象条件下で、強制避難人口850万人、自主避難人口1600万人に及ぶ。また、玄海原発4号機(佐賀県)で火災事故が起きた場合、同じ2021年9月の気象条件下で、国内の強制避難人口は2800万人、自主避難人口は2000万人に及ぶ。 ↩︎
- 福島第一原発から環境中に放出された放射性物質の量と移動様態については様々なモデルやシミュレーションによる推計があり、定量的な評価にはかなりの幅があるが、日本学術会議(総合工学委員会 原子力事故対応委員分科会)の2014年9月2日付の報告「環境中に放出された放射性物質の輸送沈着過程に関するモデル計算結果の比較」( https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf )によれば、大気への総放出量のうち陸域に沈着した比率は27 ± 10%に留まったとされている。
青山道夫・山澤弘実・永井晴康(2018)「福島第一原発事故の大気・海洋環境科学的研究の現状」『日本原子力学会誌』 60(1):46-50( https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja )によれば、事故時に炉内に存在したセシウム137のうち15-20PBqが大気に放出され、その約80%が西部北太平洋に降下したと推計される。これとは別に、3.5±0.7PBq(大気への放出量の42-86%に相当する量)のセシウム137が海に直接漏出したと推計されている(ib. p.47)。 ↩︎ - 『朝日新聞』2023年8月8日付朝刊「原発の安全対策5.8兆円 事故後、11社の総額 朝日新聞社アンケート」 https://digital.asahi.com/articles/DA3S15711697.html ↩︎
- 原子力資料情報室調べ。松久保肇「原子力小委員会のとりまとめを受けて」(2022年12月8日) https://www.ccnejapan.com/wp-content/20221208_CNIC_CCNE_PressConference.pdf ↩︎
- 原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道』(2022)p.175参照。また、p.177では、次のような専門家のコメントも紹介している。
“「現在の地震科学で将来が正確に予測できる」と思うほうが余程「非科学的」なのである。「敷地ごとに震度を特定して策定する地震動」も本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発において、基準地震動の最大加速度は少なくとも既往最大の1700 ガルにすべきである”(石橋克彦・神戸大学名誉教授)
“「震源を特定せず策定する地震動」について、原子力安全基盤機構(JNES)の算出したM5.5~M6.5 の地震による震源近傍での1,000 ガル以上の地震動は現実にも発生する可能性が高く、これを設定すべきである”(長沢啓行・大阪府立大学名誉教授) ↩︎ - 2024年3月2日、柏崎市が主催した「複合災害時の避難の在り方に関する講演会」で、田中俊一氏は以下のように発言した。(柏崎市のウェブサイトに掲載された講演会発言内容全文から一部抜粋。下線は引用者)
「それから、もう一つここで申し上げたいのは、今年は雪が少ない年ですけれども、この裏日本、特に新潟県は年によっては非常に大雪に見舞われて、交通機関が麻痺したり、道路を車も通れないような事態が起こるという年もあります。こうした自然災害、大災害と、併せて原子力事故、原子力災害が起きたときに、どうしたらいいんだっていうのが皆さんの大きな懸念事項であり、関心だと思います。 福島で13 年前に起こりました事故はまさにこのような事態でありました。複合災害が起きたときにどのようにしたら良いか。国が言うように、自宅退避はできないのではないかっていう疑問も多いかと思います。非常に困惑しているのではないかと想像されます。これから説明でおいおい詳細を説明させていただきたいと思いますけれども、答えは、複合災害のときは、原子力災害のことを忘れていただきたい。まず原子力災害を忘れて他の自然災害、他の災害から自分の身を守り、命を守ることに専念していただきたいということであります。 急にそんなこと言われたって、原子力災害を忘れてって言っても、そんなふうにはいかないと、放射線被曝の、もう非常に怖いというのが本音だと思います。本日から13 年前、起きた東京電力福島第一原子力発電所この事故の時、私もずいぶん福島に深く関 わってきました。そこで学んだ教訓を皆様にお伝えしたい、今日はお伝えしたいと思います。 原子力災害は、皆様が思い込んでいるほど、そんなに怖いものではない。これも結論みたいなこと言うと怒られるかもしれませんけど、一番怖いのは怖いという心、気持ち、それから不安と恐怖心 にかられるということであるということを今日はご説明させていただきたいと思います。」 ↩︎ - 原子力資料情報室 高木仁三郎「柏崎刈羽原発大事故時の災害評価」1992年9月 https://cnic.jp/files/KKACC1992.pdf この論文は、脚註2の「原子炉安全研究 WASH-1400」(1975)で例示された沸騰水型原子炉の事故が、柏崎刈羽原発1号機で発生した場合について、実際の日本の人口分布などをもとに分析したものである。論文中で高木は次のように述べている。「このWASH-1400の手法に基づく想定評価が、果たして最大限評価といえるかどうかは、大いに疑問のあるところであるが、一応広く行われている手法なのでここでも採用した。」また高木は、被ばくによるがん死のリスク係数について次のように述べている。「合計の集団線量は、420万人シーベルト(約4.2億人レム)にも達するもので、今、がん死のリスク係数を1万人シーベルトあたり1000とすると、約42万人のがん死者が将来において発生することになる。このがん死のリスク係数は、原爆被爆者についての最近の知見に照らしてむしろ控えめなものと考えられる。しかしより低い推定値であるICRP-1990年勧告の1万人シーベルトあたり500という値をとっても、このケースの事故によるがん死は21万人に達すると予想され、とうてい社会的に許容できない災害をもたらす。」 ↩︎
- 『原発ゼロ社会への道 ――市民がつくる脱原子力政策大綱』(2014)4-3「立地審査指針を適用しないという重大な改悪」p.143 など ↩︎
- 原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道』(2022) p.144、p.188、p.237 ↩︎