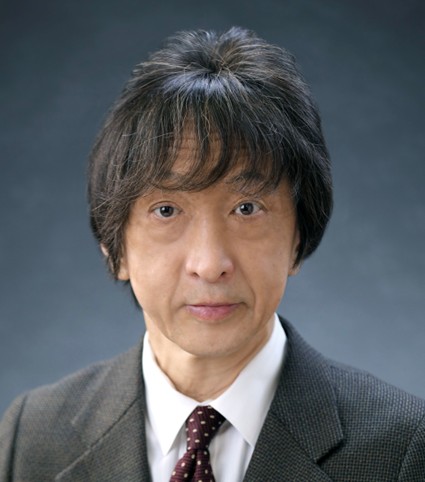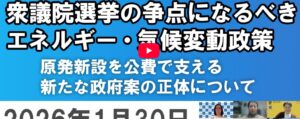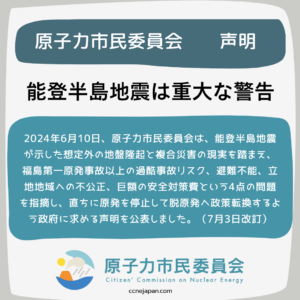電気料金のレシートを見ると、再エネ固定価格買取制度(FIT)による再エネ賦課金が特出しされているので、再エネだけにお金を余分に払っているという印象を持つ人が多いようです。しかし、これは誤解です。
FITは、1978 年に米国で最初に導入された後、ドイツなどでも導入され、再エネの大量普及および生産コスト低下に成功しました。この結果を踏まえ、現在では多くの学術的報告や公的機関がその優位性を認めています。採用国数は特に2005年以降に急増し、日本が導入する前の2009年時点では少なくとも50以上の国々と25以上の州・地域で採用されていました。
このFITによる再エネ賦課金は、短期間で再エネを普及させることを目的として導入された制度であり、買取価格は供給量や価格を考慮しつつ、だんだん小さくなっていき、一定期間後にはゼロとなります。実際に、ドイツなどでは2020年代前半で再エネ賦課金の大幅な低下が想定されており、主要国の中でも最も導入が遅かった日本でも2030年頃をピークに大幅に下がることが予想されています。
日本は他国に比べて大幅にFIT導入が遅れただけでなく、賦課金の額や認証方法等に関する当初の制度設計に問題がありました[1]。日本での再エネの価格は国際価格に比較してまだ高いのですが、このような制度設計によって競争原理がうまく機能しなかったことも大きな要因であり、それは賦課金の大きさにも影響しています。それでも、現政府でさえも、2021年の発電コストWGの試算において2030年には再エネが最も安価になるとしました。再エネ普及を阻害している電力市場の是正や電力自由化の徹底などを実施すれば、より早期に安くなります[2]。また、日本では原発に対しても、下記で示すようなさまざまな補助金あるいは税金がつぎ込まれています。しかし、それらは再エネ賦課金のように電気料金の中で見えるようにはなっていません。
「今こそ知りたい エネルギー・温暖化政策Q&A」p17ページ「3)再エネ賦課金」の「コラム:再エネ賦課金の誤解」
[1] 当初の太陽光発電への買取価格がそのときの状況を考慮しても高すぎ、かつ認可時期と建設時期のずれを許容したことも大きな禍根を残しました。現在、賦課金の大部分を、この初期の高額の太陽光発電への買い取り金が占めています。なお、日本で再エネが高いのは、原発が優先され、供給が需給を上回った場合に再エネ発電が出力抑制される制度や原発や火力発電を補助金などで温存するような制度が存在していることなども大きな要因です。ある程度の再エネの出力抑制は必要ではあるものの、その量が不確定で大きくなれば、再エネ電力を供給しようとする業者にとってはコスト高になります。また、原発や火力発電への補助金などの政策的支援は再エネの導入量を減らすことで、再エネの導入量増加による価格低下を妨げます。
[2] 2022年4月からFIT制度はFIP制度に変わっています。FIP制度とは「フィードインプレミアム(Feed in Premium)」の略称で、発電事業者が再エネで発電した電力を卸電力取引市場で自由に売電させ、そこで得られる売電収入に「あらかじめ定める売電収入の基準となる価格(FIP価格)と市場価格に基づく価格(参照価格)の差額(=プレミアム)×売電量」の金額を上乗せして交付する制度です。FIT制度のように、固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定の補助額(プレミアム)を上乗せすることで、再エネ導入を促進すると政府は説明しています。具体的には、政府は、1)プレミアム分は電気使用者から徴収する賦課金で賄われるものの、FIT制度と比べると比較的少ない金額に抑えることができる、2)参照価格は一定期間(1ヶ月~1年程度)毎に変更することで、事業者の投資予見性確保と、市場価格を意識した発電行動促進の両立が実現できる、などとしています。