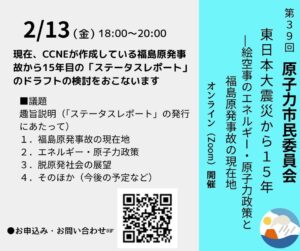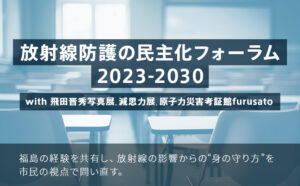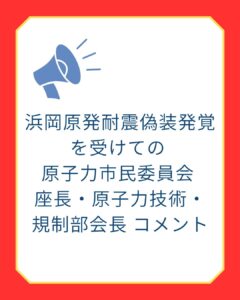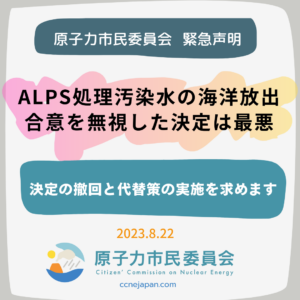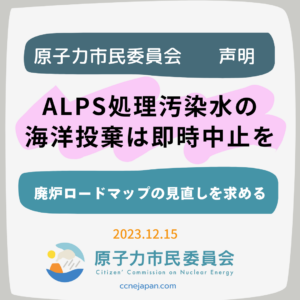原発事故による放射性物質放出をどう予測するか – 柏崎刈羽原発が重大事故を起こしたら?
*6月17日(火)当日録画記録:CCNE連続オンライントーク「原発ゼロ社会への道」2025 第2回
『柏崎刈羽原発ーゆるされざる再稼働(シリーズ その2)』
前回のオンライントーク(柏崎刈羽シリーズその1 www.ccnejapan.com/?p=16165 )では、東京電力柏崎刈羽原発6号機と7号機の原子炉の構造自体がはらむ深刻な危険性について解説しました。その後、6月10日、東京電力は6号機の燃料装荷作業を地元同意を待たずに始めてしまいましたが、再稼働した場合、重大事故が起こりうることは決して小さくないリスクであることが技術的に明らかです。では、事故が起きても住民の安全は確保できるという政府や電力会社の説明には科学的根拠と現実性があるのでしょうか。
原発再稼働にあたって、地域の防災計画(とりわけ避難計画)では東京電力福島第一原発事故の教訓をふまえると言いながら、実際には、福島原発事故での放射性物質放出量よりもずっと少ない規模の事故しか想定しないなど、多くの問題があります。再稼働のための適合性審査では福島原発事故以前よりも厳しい安全設備が要求されているなどの理由で、放出量が「福島並み」にはならないと想定されているのです。福島並みの規模を想定すると避難計画そのものが成り立たないという裏の理由もあるのでしょう。しかし、そもそも福島原発事故の規模自体が数々の幸運によって「最悪シナリオ」を辛うじて免れた、つまり、「福島並み」を上回る事故になっていても全く不思議はなかった ── これこそ、忘れてはならない「福島の教訓」のひとつではないのでしょうか。
新潟県は、福島原発事故についての「三つの検証」[i]を自治体として独自に進めるなど、原発立地県としての気概をいったんは示しました。三つの検証は、泉田裕彦知事の「福島事故の検証なしに、再稼働の議論はしない」という強い姿勢を受け継いだ米山隆一知事が2017年に始動しましたが、花角英世・現知事(2018〜)になって、東京電力の適格性や柏崎刈羽原発の事故の可能性を議論に含めることが抑制されるようになり、「検証総括委員会」は2023年3月、県によって一方的に打ち切られました。そうした経緯については、2023年11月のオンライントークで佐々木寛さんから詳しい報告をしていただきましたので、ぜひ御覧ください(http://www.ccnejapan.com/?p=14557)。(なお、佐々木さんには、次回7月4日のオンライントークに再度ご出演いただく予定です。)
この三つの検証のひとつとして「原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」(避難委員会)を立ち上げて専門家による議論が公開のかたちでおこなわれました(2017〜2022年)。この委員会では、福島第一原発で実際におきた事態をふまえ、柏崎刈羽原発での重大事故についても防災避難の観点からシミュレーション(想定実験、予測試算)をおこなうべきとの意見があったのですが、結局、報告書ではシミュレーションの重要性や留意点(設定によって結果が大きく変動すること、など)が列挙されるに留まりました[ii]。県による検証体制が尻つぼみに終わったあと、三つの検証の元委員らを中心に「市民検証委員会」( https://shiminkenshouiinkai.jimdosite.com )が独自に検証作業を続け、柏崎刈羽原発の事故による放射性物質の放出・拡散のパターンについても、何通りかのシミュレーションがなされました。
一方、新潟県は今年5月16日に柏崎刈羽原発で事故が起きた場合に予測される被ばく線量の試算結果を公表し、「IAEAの基準を上回る被曝をさけることができる」としています[iii]。IAEAの基準とは、「緊急時に対策を必要とする基準」とされている1週間あたり100mSv(ミリシーベルト、実効線量)ですが、5㌔圏内(PAZ)では基準を超える場合があるものの、PAZでは放射性物質の放出以前に避難が行われる想定なので被ばくは回避されると評価しています。しかし、一般公衆に対する法定の追加被ばく限度は年間でも1mSvなのに、これを全く無視して桁ちがいに大きな被ばくを基準としています。これは「事故時には住民の被ばくもやむをえない」というのを前提としているからですが、そのような法的根拠はなく、誰も同意していません。国の原子力災害対策指針では、空間線量率500μSv/h(1時間あたり500マイクロシーベルト=0.5mSv/h)で避難、または20μSv/h(1時間あたり20マイクロシーベルト)で一時移転が必要と判断することになっているのに、県は空間線量率については結果を示さず無視しています。現地の実際の気象条件をあてはめて試算すると、条件によっては30㌔圏(UPZ)を超える地域でも避難や一時移転が必要となる場合があることが推定されています。
そもそも、県のシミュレーションでは、事故で放出される放射性物質の量を福島原発事故の放出量(実績)の1万分の1に想定しています。花角知事は県議会での答弁で「過度な想定は不安をあおる」としていますが[iv]、過小想定の土台のうえに構築された防災計画で住民の安全は確保できるのでしょうか。
今回のオンライントークでは、「三つの検証」の避難委員会の委員をつとめ、市民検証委員会にも参加されている上岡直見さんをお迎えして、事故時の放射性物質の拡散予測を試みる際の考え方、想定の立て方、そして市民検証委員会のシミュレーションと新潟県のシミュレーションの違いをどう見るか、といった一連の問題を解説していただきます。
皆さま、どうぞお誘いあわせのうえ、ふるってご参加ください。
- 日 時: 2025年6月17日(火)17:00~18:00
- 場 所: オンライン開催(zoom)
- プログラムと出席者:
- 「原発事故による放射性物質放出をどう予測するか─ 柏崎刈羽原発が重大事故を起こしたら?」
- 上岡直見さん(環境経済研究所 代表、新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会 元委員)資料
参考資料:経済被害推定報告書
- 上岡直見さん(環境経済研究所 代表、新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会 元委員)資料
- 質疑応答・意見交換
- 「原発事故による放射性物質放出をどう予測するか─ 柏崎刈羽原発が重大事故を起こしたら?」
- (この企画は、後日Youtubeで公開します。Zoomのウェビナー形式で開催し、ご質問やご意見は当日の質疑応答(Q&A)もしくは、後日メール・FAXなどで受けつけます)
- 申し込み: 下記よりお申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ObZJA-V9SJulYLtTWirumA
※ 案内が届かない場合は、email◎ccnejapan.com(◎は@に変えてください)までお知らせください。 - 主 催: 原子力市民委員会
- お問い合わせ:email◎ccnejapan.com[◎を@に変えてください] TEL 03-6709-8083
脚注
[i] 新潟県「福島第一原発事故に関する3つの検証について」https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/kensyo.html
[ii] 新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会「福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力災害時の安全な避難方法の検証~検証報告書~」(2022年9月21日) https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/335132.pdf
[iii] 朝日新聞新潟版 2025年5月17日「柏崎刈羽原発の被曝線量予測を新潟県が公表 5キロ圏内で基準値超え」 https://digital.asahi.com/articles/AST5J4CTMT5JUOHB007M.html
[iv] 新潟日報 2025年1月11日「新潟県による被ばく線量シミュレーション、想定に『新たな安全神話』の懸念」 https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/534651