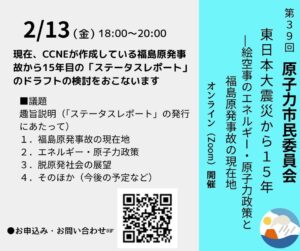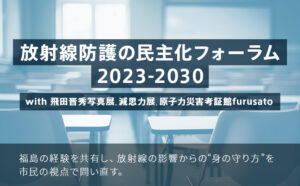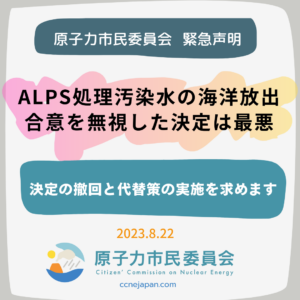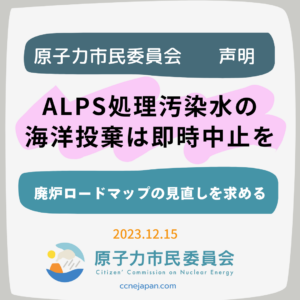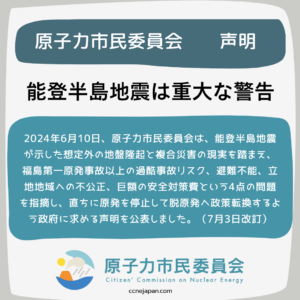2025年9月10日
声明:放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである
原子力市民委員会
座長 大島堅一
委員 後藤忍 後藤政志 清水奈名子
茅野恒秀 松久保肇 武藤類子
吉田明子
日本政府は、2025年6月20日に「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」(以下、復興基本方針)を閣議決定した[1]。今回の復興基本方針では、2023年8月に策定した「特定帰還居住区域における放射線防護対策について」[2]を踏まえ、新たに次のような方針を打ち出している。
1)帰還困難区域における「バリケード等の物理的な防護措置を実施しない立入規制の緩和を行う」こと
2)「森林整備の再開を始め、「区域から個人へ」という考え方の下で、安全確保を大前提とした活動の自由化」を検討すること
3)山菜やきのこなどの食品等に関する規制等について「特別の区分の基準を設けて対応する」ことや、「検査をして安全性を担保された自家消費食品の摂取制限を見直す」こと
このような記述は、あたかも国が安全性を担保したうえで実施されるかのようにみえる。しかし実際には、放射線被ばく量や食品摂取量の管理を個人の自己責任に委ねるものになっている。帰還困難区域における特定復興再生拠点区域外の地域の全面的な除染の見通しは一切含まれていない。つまりこれらの施策は、放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁し、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を放棄するものと言わざるをえない。まさに原子力市民委員会が指摘した「無責任の構造」[3]が、ここに現れている。
帰還困難区域がある自治体の住民の声として復興基本方針で示されているのは、「帰還の早期実現を求める声」や「山の恵みを取り戻したいという地域の声」のみである。それらが、事故被害にあった住民の切実な願いであることは疑いの余地がない。しかしここで問題なのは、国が汚染に対する自らの責任に関わることを取り上げていないことである。住民の間には、帰還困難区域の森林を含む「全面的な除染」を求める声が確かに存在している。これは、国に放射性物質対策を強く求める声であり、国が真っ先に取り上げ、その実行可能性をも含めて誠実に回答すべきものである。
事実、「特定帰還居住区域における放射線防護対策」では、住民が帰還し生活する中で個人が受ける追加被ばく線量を、長期的には年間1ミリシーベルト以下に抑えることを目標とするとされている。しかし、事故から14年が経った現在もこれは依然として「長期目標」にとどまり、その実現のための具体的な政策は示されていない。
実際には、特定帰還居住区域の設定や帰還困難区域での活動においては、いまだに「年間20ミリシーベルト以下」という基準が適用されている[4]。さらに、認定された自治体の特定帰還居住区域復興再生計画[5]には、区域の一部で20ミリシーベルトを超える地点が存在することまで明記されている。
復興基本方針によって現実に懸念される事態としては、次のような点が考えられる。
1)放射線量の高い区域に誤って人が立ち入ってしまうこと
2)個人の被ばく量の管理が不十分になること
3)子どもも大人と同様に被ばくしてしまうこと
4)健康被害が生じた場合の責任主体が曖昧になること
5)森林整備等によって放射性物質が再飛散・移動するリスクがあること
6)「規制緩和=安全」と誤解され、リスクを過小評価したり誤った判断を誘発すること
これらの事態は決して生じてはならず、その防止に向けた明確な対策と責任が問われている。
総じて、復興基本方針は、全面的除染と避難指示解除をしないまま、帰還困難区域における活動を認めるものになっている。これは、「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする」ことを「国の責務」とした放射性物質汚染対処特措法に反している。復興政策において、国は、放射能汚染に対する責任を全うするべきであり、放射線被ばくの管理責任を、事実上個人に任せるような措置を執るべきではない。原子力市民委員会は、復興基本方針の見直しを強く求めるものである。
以上
[1] https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20250617160512.html
[2] https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2023/20230815honbun.pdf
[3] 原子力市民委員会(2022)『原発ゼロ社会への道 ――「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』
[4] https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2024/240601_katsudounitsuite.pdf.pdf
[5] https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/saiseikyoten/20230928101604.html