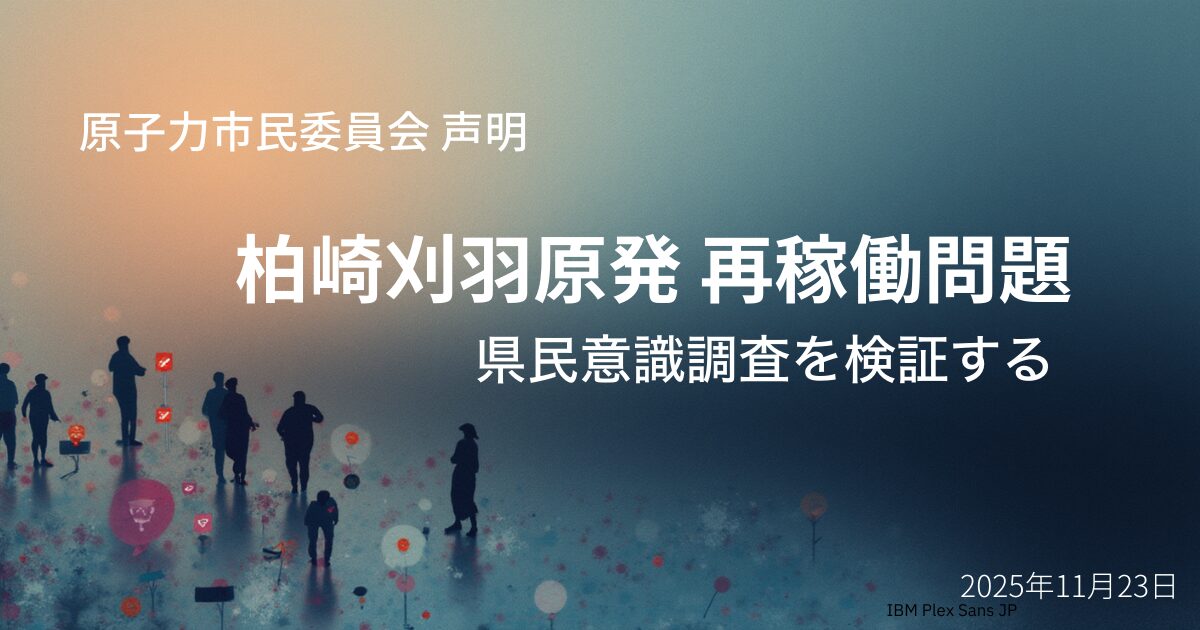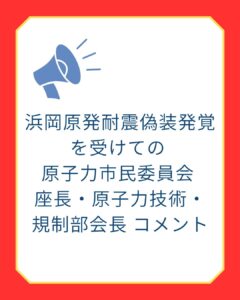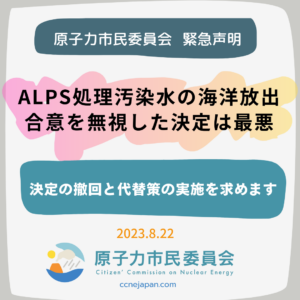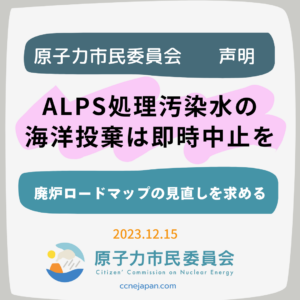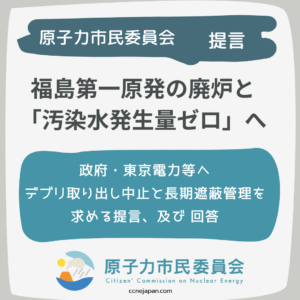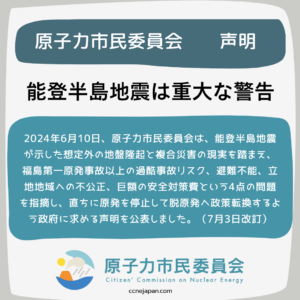声明: 花角新潟県知事の判断は県政と日本の原子力エネルギー政策全体に大きな禍根を残す ——県民意識調査を検証する——
2025年11月23日
原子力市民委員会
座長 大島堅一
委員 後藤忍 後藤政志 清水奈名子
茅野恒秀 松久保肇 武藤類子 吉田明子
【要約】新潟県が実施した柏崎刈羽原発の再稼働についての「県民意識調査」は、質問順による回答誘導や誘導的な説明文など、社会調査の手法として避けるべき基本に反している。そのような誘導にもかかわらず、再稼働へのさまざまな面での懸念を示す回答が多数を占め、再稼働容認が県民の総意であると解釈するのは無理がある。知事が重視するとした論点も解消されておらず、この調査を根拠とする再稼働容認判断は妥当性および正当性を欠き、県政と日本の原子力政策に重大な禍根を残す。
- 新潟県による「県民意識調査」には、質問配置によるキャリーオーバー効果、一面的で誘導的な説明、複数論点を一問に含むダブルバレル質問など、社会調査として看過できない重大な欠陥をはらむ。
- 知事が重視するとした「必要性・安全性・東電への信頼」の3論点のうち、少なくとも安全性と信頼性は解消されていない。
- 調査結果からは、安全性・防災対策・東京電力への信頼性のいずれも県民の懸念が強く、「再稼働の条件が整っている」との回答は37%に留まる。
2025年11月21日に、花角英世・新潟県知事は東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を容認するとの判断を表明した。知事は、この判断に至る過程で、県内市町村長の意向とともに、県が主催した公聴会と県民意識調査の結果をふまえてきたという。
しかし、2025年9月~11月に県が実施した「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査」(以下、県民意識調査)には、以下に記すような問題がある。この調査結果とその解釈をもって、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識を、実像に迫る形で把握できたとは言い難い。今回の知事の判断は不適切である。
県民意識調査は、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題について、県民の多様な意見を把握するため、地域・年代・性別等の幅広い属性を対象に実施されたもので、県内30市町村の6,000人に調査票を送付した大規模なものである。10月~11月にはPAZ・UPZ地域を対象とした追加(補足)調査を6,000人に実施した。
県民の意見を広く把握しようとする試みは基本的に歓迎すべきものである。しかし、仮に調査設計が対象者に特定の結論を誘導しかねないものであったり、調査結果が恣意的に解釈されたりするようなことがあれば、その価値はたちまち失墜する。多額の公金を投じる意義も問われ、県民生活の安全を守る県の立場は厳しく問われるであろう。
脱原発をめざす市民や技術者、研究者らによって組織された原子力市民委員会には、社会調査の経験を積んだ社会学者・社会科学者が委員やアドバイザーとして複数参画している。私たちは県が公表している調査票や報告書の内容を精査し、以下の問題点を確認した。
新潟県が行った県民意識調査は、社会調査や科学の基本的な作法から逸脱しており、この調査結果から、県民が柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に理解を示しているとは言い難い。知事の判断は、正当性がなく、新潟県にとっても、また日本の原子力エネルギー政策全体にとっても大きな禍根を残すものである。
1.調査票の設計に関する問題
「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査 調査票」には、以下の問題点がある。なお、調査票は11の大問からなるが、細分化された小問や小項目をカウントすると、調査対象者は総計43の質問に回答するものとなっている。
1.1 前の質問が次の質問に影響を与える「キャリーオーバー効果」を引き起こす配置になっている
調査票は最初の質問(問1)で「柏崎刈羽原子力発電所に限らず、日本における原子力発電所の必要性」について問うている。
この質問の配置は、前の質問の回答が続く質問への回答に影響を与えてしまう「キャリーオーバー効果」を引き起こすおそれがある。具体的に言えば、続く質問で聞かれた柏崎刈羽原子力発電所に関する評価が、日本における原子力発電所の必要性に関する回答と矛盾しないように、一定数の回答者に意識させてしまった可能性がある。
社会調査法に関する教科書の多くで、キャリーオーバー効果は影響を与えそうな質問の順番を変えることで避けられるとしている[1]。柏崎刈羽原子力発電所という県民意識調査の主題の範疇を超える質問は調査票の終盤にまわすなど、調査票設計上の工夫の余地は十分あった。「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」をうたいながら、調査票の冒頭で「日本における原子力発電所の必要性」という、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題の範疇を超える一般論に関する意識を問うたことは社会調査の基本的作法からみて誤りである。
1.2 誘導的な内容が含まれている
問4-2は、柏崎刈羽原子力発電所の「防災対策」に関して、避難計画の策定から防災訓練の実施まで8つの取り組みに対する認知度を問うている。調査票には8つの取り組みに関する補足の情報が各項目の下部に記載されているが、避難計画や避難路の整備、除排雪体制の強化などの内実については、それぞれに多様な評価が存在し、公聴会等においても論点となってきた。にもかかわらず「訓練等を通じて連携を深めています」(項目(3))といった一面的な評価が含まれた説明が施されている点は、調査対象者の意識をある方向へと誘導することにつながりかねない。
続く問4-3では、防災への取り組みの実施度に関する評価を問うており、誘導的な内容を含む質問への回答が、上述したキャリーオーバー効果を引き起こすおそれもある。問3-1と問3-2の関係も同様である。
なお、問4-2には誘導質問となる可能性の他にも問題がある。それは、項目と説明が併記され、説明の情報量が多く複数の論点にまたがるため、回答者は何について「知っている」「知らない」を判断すればよいか、にわかに識別し難い。質問の中に複数の論点や対象を盛り込むことは「ダブルバ-レル」と呼ばれ、一般に避けるべきであることは社会調査の基本的作法である。
2.調査結果の解釈に関する問題
新潟県が公表した報告書の集計結果をそのまま読めば、県が主題とした「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題」に関わるポイントは以下の3点にまとめることができるだろう。
2.1 柏崎刈羽原子力発電所の安全性や防災への取り組みに対する評価は低い
1.で見たように、問1などキャリーオーバー効果が生じているおそれがある、または問4-2など誘導的な内容となっているおそれがある質問を含む調査票で実施された調査にもかかわらず、回答者の多数は、安全性や防災への取り組みに対する懐疑的な意識、または「わからない」とする意識を有していることが明らかである。例を挙げよう。
- 柏崎刈羽原子力発電所で実施されている対策により、安全性が「十分/おおむね確保されている」と回答した県民は44%にとどまる(問3-2)
- 防災への取り組みは「十分/おおむね実施できている」と回答した県民は36%にとどまる(問4-3)
この結果を、県(ならびに事業者、事業監督者)は重く受けとめなければならない。
2.2 再稼働の条件は現状では整っていない
問5-1は柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機の再稼働に関する考え方を複数例示し、それぞれに同意するかを問うている。同意する(「そう思う」と「どちらかと言えばそう思う」の合計)割合の多い順は次の通りであり、使用済核燃料の問題や原子力災害の発生に対する不安感がほとんどの回答者に認識されている。
(12)「使用済核燃料が増えていくことが問題だ」(92%が同意)
( 5 )「豪雪時に安全に避難/屋内退避できるよう、除雪体制のさらなる整備が必要だ」(同91%)
(10)「原子力災害が発生した場合、風評被害が起きないか心配だ」(同91%)
(11)「原子力災害が発生した場合、十分な補償が受けられるか心配だ」(同91%)
一方で、問5-1において同意する割合の最も少ない考えが、(14)「再稼働の条件は現状で整っている」(同37%)であったという事実を無視してはならない。
2.3 知事が認識する3つの論点のうち、少なくとも2つは解消されていない
加えて、問5-1の結果は次のような内容が含まれている。
(8)「地域経済や雇用に良い影響がある」(同67%)
(9)「自分の住む地域にさらなる具体的なメリットが必要だ」(同69%)
これらの経済的メリットに関する期待や同意は過半を超えている。しかし、花角知事は2024年9月4日の記者会見で、再稼働をめぐる論点は原発の必要性と安全性、東京電力への信頼性の3つであり、経済的メリットはこれら3つの論点とは水準が異なるとの認識を自ら示している[2]。
東京電力が柏崎刈羽原発を運転することについては、以下のような結果がでている。
(2)「東京電力が柏崎刈羽原子力発電所を運転することは心配だ」(同69%)
知事が認識する3つの論点のうち少なくとも2つ、すなわち原発の安全性と東京電力への信頼性は、解消されていないことが明白である。
3. 県民意識調査は、新潟県知事の再稼働容認の根拠にならない
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関わる県民の意識はある程度明確に示されている。とりわけ問5-1(14)において、「再稼働の条件は現状で整っている」との考えに同意する回答者は全体の37%にとどまったことは重大である。
にもかかわらず、報告書では安全対策や防災対策に関する認知度、つまり県民の知識量が増えるほど「再稼働の条件は現状で整っている」と思う割合が高くなる傾向にある(報告書、p.91-92)といった「詳細分析」が繰り返されている。これは人々の科学技術に関する知識の欠如が問題が解決されない原因であるとみなし、知識を増やせば問題が解決するという「欠如モデル」に基づく仮説である。この考え方は、科学技術社会論や科学技術コミュニケーションの領域では、すでに有効性を失っているものである。
県民意識調査の結果は、今般の知事の判断の根拠とはならない。東京電力が柏崎刈羽原発を再稼働することは、新潟県民の意思から乖離しており、許されない。
※ 県民意識調査について
・調査票は以下のウェブサイトで確認することができる
新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査の実施について」(2025年9月3日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/kashiwazakikariwa-kenminishikityosa-tyousakaishi.html
・調査結果は以下のウェブサイトで確認することができる
新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査の結果」(2025年11月11日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/kashiwazakikariwa-kenminishikityosa-kekka.html
脚注
[1] 例えば、大谷信介他『最新・社会調査へのアプローチ』ミネルヴァ書房、2023年など
[2] なお、実際に経済的メリットがあるかどうかについては、検討の余地が残されている