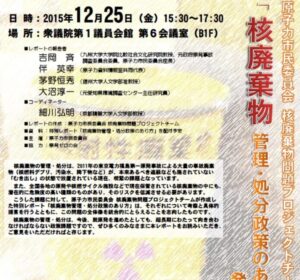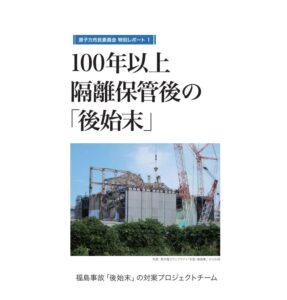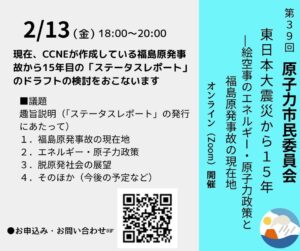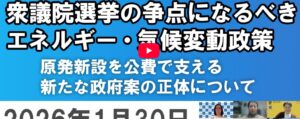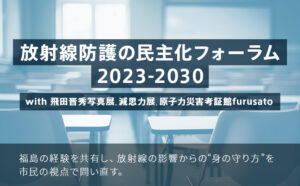政府・東京電力は、福島第一原発事故の廃炉を、「中・長期ロードマップ」に基づいてすすめています。「中・長期ロードマップ」では、最長40年(2051年12月まで)で廃炉が終了することが想定されていますが、メルトダウンしたデブリをすべて取り出し、福島第一原発を更地に戻すことができるかのような前提で議論されており、もっとも重要で困難な課題があいまいにされたままです。
「日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」が2020年に発表したレポートでは、福島第一原発の廃炉で発生する放射性廃棄物の推計値として、合計783万トンという数値が示されています[1]。これは、同じレポートで示された、通常の沸騰水型原発の廃炉で発生する放射性廃棄物(12,740トン[2])の600倍以上という途方もない量です。この783万トンには、燃料デブリも含まれていますが、果たして回収できるのか、それを何らかの容器に保管し、どこかに確保した処分場に運び出すことができるのか、技術的にも社会的にも極めて困難な課題であり、そのための現実的な議論すら先送りにされているというのが実情です。
福島第一原発では、いまだに放射線量が高く、人が立ち入れないような箇所が残されており、この原発を解体し、放射性廃棄物をすべて処分するためには、膨大な被ばく労働が避けられません。現状は、作業方法などを技術的に検討している段階であり、福島第一原発が更地になるような「廃炉」は、およそ見通しが立っていない状況です。原子力市民委員会としては、むしろ工程を急ぐのではなく、時間をかけて、放射能が減衰することを待つのが賢明だと考えています。そのためにも、福島第一原発の廃炉は、100年以上の長い時間軸で考えるしかないというのが原子力市民委員会の考えです。
ALPS処理汚染水の海洋放出や、除染で発生した汚染土の処理などでは、薄めた「処理水」を海に流すことや、基準以下の「除去土壌」を普通の生活環境での工事に使うことが、安全上、問題ないとされ、それが「復興」の重要なステップであるかのような説明がありますが、福島第一原発には、極めて放射能レベルが高い「汚染水」や「燃料デブリ」などが存在しており、それらを安全かつ確実に処理することができるかどうかに「廃炉」の成否がかかっています。廃炉が40年で完了するような「中・長期ロードマップ」は、現実とはかけ離れた「絵に描いた餅」だと言わざるを得ません。
[1] 『国際標準からみた廃棄物管理 -廃棄物検討分科会中間報告―』(2020年7月、日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会)p.19「表3.4-2 1F廃炉・サイト修復で発生する放射性廃棄物の試算例」では、放射性廃棄物の区分ごとに、燃料デブリ644トン、HLW(高レベル放射性廃棄物相当)2,125トン、TRU(超ウラン元素相当)846トン、L1廃棄物282,068トン、L2廃棄物2,221,800トン、L3廃棄物5,329,588トン、合計7,837,071トンとの数値が示されている。当然ながら、放射性廃棄物はその汚染のレベルが高いほど、管理・処分が困難であり、レベルの違う放射性廃棄物の量を単純に合計することは本質的ではないが、ここでは福島第一原発の廃炉で発生する放射性廃棄物の総量が、通常の原発の廃炉で発生する廃棄物と比べて、桁違いに多いということを理解していただくために、あえてこのような書き方をした。
[2] 同報告書p.10「表2.4-1」に、大規模BWR(沸騰水型原発)の廃炉で発生する放射性廃棄物として、L1廃棄物80トン、L2廃棄物850トン、L3廃棄物11,810トンという数値が示されており、これを合計すると12,740トンとなる。